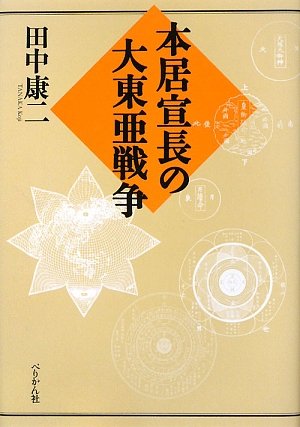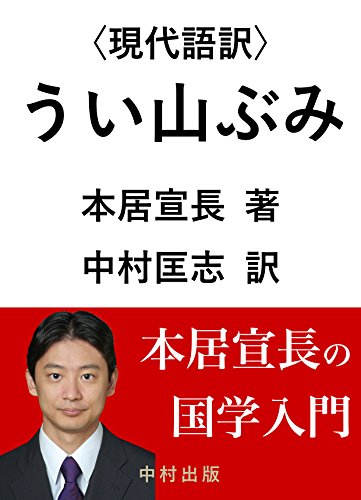少し前に、神道に興味が出たと書いた。
その後、この新書を読んだ。
神道についてのスタンダードな歴史を追えた。日本の「神」が「成仏させてくれ」と仏にすがるみたいな話も多かったらしい。
おもしろすぎるのが欠点、と評されてなんかの賞をとった本。たしかにおもしろい。でも、いちばん気になったのは本居宣長の「神」の定義だった。
さて凡て迦微とは、古御典等に見えたる天地の諸の神たちを始めて、其を祀れる社に巫ます御霊をも申し、又人はさらにも云ず、鳥獣木草のたぐひ海山など、其余何にまれ、尋常ならずすぐれたる徳のありて、可畏き物を迦微とは云なり。(すぐれたるとは、尊きこと善きこと、功しきことなどの、優れたるのみを云に非ず、悪きもの奇しきものなども、よにすぐれて可畏きをば、神と云なり。」(『古事記伝』三之巻)
宣長のいうところは、それが人であれ、動植物であれ、自然現象であれ、ともかくもそのものが、私たちにとって「可畏き物」、すなわち身の毛もよだつような異様なものとして出会われれば、それが神なのだということである。(略)日本語の「カミ」という言葉のニュアンスをよく言い当てている。と同時に、人格的な唯一創造主ゴッド(God)に、神という訳語を当てたことが、わが国の翻訳史上、最大の失策であったことをも納得させてくれる。
これが神だとすれば、「日本は神国である」といったときのニュアンスはずいぶん変わるのではないか。「悪きもの奇しきものなど」も神なのだ。
おれは本居宣長に興味を持った。
とりあえず、本居宣長ってどんな人だっけと、新書を読んだ。たしかに文学と思想の巨人だ。歌論をはじめ、文献学と呼べるほどの実証主義をとって言葉を論じた。今の学校教育の「古文」の係り結びだのなんだのは、本居宣長(とその息子)がほとんど完成させた。五十音表の「お」と「を」の位置を正しくした。そして、『古事記』研究に、「もののあはれを知る」論に、漢意批判と、まあいろいろやったんやな。巨人やな、という印象。もちろん、『馭戒慨言』あたりが幕末の志士、尊王攘夷の必携の書になったり、その後の愛国主義、軍国主義に利用されたのもとうぜんという物言いもしているのだが。
そして、けっこう本格的に分厚くむずかしそうなこの本を読んだ。『神道の逆襲』の著者によるものだったから。これは本居宣長の歌論や『源氏物語』研究における文献主義、実証主義を検証し、ある種の客観的な基準というものが生まれ、その定格・変格などによって言葉の正・不正を見分け、やがては『古事記』に至ったのだ、という本、だと、思う。著者はあくまで本居宣長の客観性についてその証拠を提出して、その『古事記』への傾倒や皇統への無根拠な信仰に見えてしまうところにも理があるのだと論じている、のだと思う。その言葉による正・不正の判断自体がどうなのかはともかく、本居宣長的には膨大な文献を緻密に研究した結果なのだと。そのあたりはおもしろく思うが、まあおれの理解が正しいかどうかはわからない。
あとは、『源氏物語』とか歌とかを儒仏の意味で読むんじゃないよ、というところで、それはそうだと思った。和辻哲郎の「もののはれ」についてから孫引き。
「もののあはれ」を文芸の本意として力説したのは、本居宣長の功績の一つである。彼は平安朝の文芸、特に源氏物語の理解によって、この思想に到達した。文芸は道徳的教誡を目的とするものではない、また深遠なる哲理を説くものでもない、功利的な手段としてはそれは何の役にも立たぬ、ただ「もののあはれ」をうつせばその能事は終わるのである、しかしそこには文芸の独立があり価値がある。このことを儒教全盛の時代に、すなわち文芸を道徳と政治の手段として以上に価値づけなかった時代に、力強く彼が主張したことは、日本思想史上の画期的な出来事と言わなくてはならぬ。
文芸の独立、これがすごい。現代では当たり前と思われている政治と道徳を離れた文芸というものの独立的価値を認めたという、画期的な存在だったのだ。そんなん知らんかった。
本居宣長自身のほかの言葉もいくつかメモしておこう。
姦邪の心にてよまば、姦邪の歌をよむべし。好色の心にてよまば、好色の歌をよむべし。仁義の心にてよまば、仁義の歌をよむべし。ただただ歌は一偏にかたよれるものにてはなきなり。実情をあらはさんとおもはば、実情をよむべし。いつはりをいはむとおもはば、いつはりをよむべし。詞をかざり面白くよまんとおもはば、面白くかざりよむべし。只意にまかすべし。これすなはち実情也。秘すべし秘すべし。
詩歌について。これを著者は「実情論というよりはむしろ実情解体論」と述べている。いつわりやかざりまで認めるとはそういうことであろうと思う。
大方、人の実の情といふものは、女童のごとく未練に愚かなるものなり。男らしくきつとして賢きは、実の情はあらず。それはうはべをつくろひ飾りたるものなり。実の心の底をさぐりてみれば、いかほど賢き人もみな女童に変ることなし。
「女童」とはけしからんとなるのが現代の道徳の水準だろうが、江戸時代の人が書いたのだからそこは考慮してほしい。幼子の心、くらいに読み替えてもいいだろう。というか、武家社会の江戸時代において「実の情(まことのこころ)」は女童だと述べたのがいかに大きなことかとは思う。むしろもう、「男らしくきつとして賢きは、実の情はあらず。それはうはべをつくろひ飾りたるものなり」なんていうのは、現代のジェンダー論というか、男性学に近いんじゃないかとか思う。
事しあれば嬉し悲しと時々に動く心ぞ人の真心
動くこそ人の真心動かずと言ひて誇らふ人は岩木か
これは「真心」について述べられていたところに引用されていたものだが、それはともかくとして、これはいいなと思う。
このあたりのことを述べた人間が、いかにして大日本帝国の愛国心を煽る結果になったのか、あるいはこういう「真心」が愛国心に直結しているのか、そのあたりは気になる。
そのあたりこの本(著者は新書の人)を読もうかどうしようか考えている。
とはいえ、本居宣長の原著を当たれよと言われそうで、そのあたり読みやすい現代語訳でもあれば考えてみよう。『うひ山ぶみ』とかからか?