
映画の帰り、伊勢佐木町の古本屋で目に入った『腰越帖』の三文字。俺は津西の育ちではあるが、腰越小学校とかいうところに通っていたこともあって、思わず手に取る。見返しを見ると源義経の「腰越状」らしき一瞬直筆かと思える筆文字あって、それならば興味ないかと思いつつパラパラめくってみれば「はしがき」にこんなこと書いてある。
……さるにても、秋風急に心にしみて、世界の風雲あわただしき此の際、わが友だちは、いかなる空の下に、いかなる燈の下に、この閑文字をひもどかれることであらう。例へば、砲煙弾雨下の戦地にある友よ、幸ひに陣中小閑を得てこの書を手にせられたならば、しばらく私と閑談して戦塵を忘れて給え。
昭和十二年秋九月、燈火管制下のほの暗き燈の下にて、
飯塚友一郎識
などとあって、当時の随筆集である。このところ奥崎謙三的なものが心に巣食っている身としては、「なにをのんきなことを!」と思わんでもないが、装幀の質感も実によく(書物展望社というわりかし人生をかけている人のやっていた出版社から出ていた)、価格千五百円とあって、競馬に負けたと思えば安いものと思って、表の百円棚にあった石母田正の『歴史と民族の発見』とともに買い求めた。
以下、鎌倉〜藤沢あたりの土地鑑ある人にはいくらか楽しめるかもしれないが、その保証もない。ちなみい、俺の出自はこのあたりを読まれたい。
- 感傷と追憶の腰越・津・西鎌倉紀行〜その1〜 - 関内関外日記(跡地)
- 感傷と追憶の腰越・津・西鎌倉紀行〜その2〜 - 関内関外日記(跡地)
- 元鎌倉市民が読む『青い花公式読本』〜井汲家宅/澤乃井家宅所在地研究〜 - 関内関外日記(跡地)
飯塚友一郎について
さて、その前に書いたのはたれかという話だ。調べてみるとウィキペディアに項目のない級の人物であった。1894−1983 大正-昭和時代の演劇研究家。
飯塚友一郎(いいづか ともいちろう)とは - コトバンク
明治27年11月11日生まれ。弁護士のかたわら歌舞伎を研究,演劇学の確立をめざす。日大,二松学舎大の教授を歴任。日本演劇学会の創立に参加し,松竹歌舞伎審議会専門委員などをつとめた。昭和58年4月21日死去。88歳。東京出身。東京帝大卒。著作に「歌舞伎細見」「演劇学序説」など。
なんというか、まったく興味なさそうな分野の人である。ただ、俺は昭和54年の生まれで、1歳になるかならんかのうちに札幌からこちらに来ていたので、すれ違った可能性くらいはあるやもしらん。この本を出したのは1937年、著者は43歳。
と、検索結果に「wikipedia:飯塚くに]なる名が見られる。読んでみれば坪内逍遥の養女であって、友一郎氏はその夫であった。なるほど、読み進めれば逍遥居士についての思い出話など出てくる。そういった人物の随筆である。
なお、夫人との縁について「松井須磨子の臨終」という一遍で語っている。著者はwikipedia:松井須磨子が自殺した藝術倶楽部の隣接した宅から大学に通っており、ある明け方に「ガターンといふ物音」を聞く。あとからそれが、彼女の自殺だったと知る。
して見ると、やはり私が一番、彼女の死の床の近くに寝てゐたわけになるのか知ら、而も、それと知らずに、臨終の物音を聞いたのも、私唯一人きりではなかつたかしら。
と、その死の二日前に彼女の劇を見ているのに、なにやら平然の感じである。まあ、書いているのがずっとのちなのだが。して、さらに夫人との因縁というのは、松井須磨子の詫びを記した遺言を最初に受け取ったのが彼女だったという話である。須磨子が甥に命じて、坪内家に届けさせたからという。そんなことはつゆ知らず、後に結婚したのである。まあしかし、べつにどうでもよろしいし、本人も「不思議な因縁である」とか言ってるだけなので、どうでもいい。
当時のあのあたり
さて本題。まず、著者は東京の生まれであって、鎌倉、腰越、土着の人間ではない。我々の中學時代、明治末にシンプル・ライフ(簡易生活)といふ言葉が流行した。たしかそうした書物が翻譯されて広く讀まれたと覺えている。
「腰越卜居」
けれども、やはり都会も田舎もまだまだ煩瑣極まる冠婚葬祭その他の交際に興味を感じ、衣食住の享楽をにわずらわされているという。
私は世帯を持つて十年ほど、そうした生活にも妥協してきたが、遂に面倒臭くなつて、ひたすら簡素な生活にあこがれた。思ひ切つて都心に食い込んでのアパート住まひか、それとも四五十キロ離れての近郊生活か? これは近代生活の二つの型だが、私は腰越に夏の山宅があるのを幸ひ、すぐにそこへ移転を敢行した。
―まだ隠居するには早いぢやないか。
―とんでもないこと、隠居どころか、うんと能率をあげるのです。
「腰越卜居」
という具合で、腰越に来た人間である。まあなんというか、なんだよこれは。こんな話、いまだにライフハックだノマドだなんだと、言われ続けていることじゃあないか。もっとも、こいつはこの時代の相当にひとにぎりの上流階級であって、多くの人間には「二つの型」を選ぶことなどできなかったわけだけれども。ただ、戦後経済成長と共に多くの人間にそういう選択を得るようになっていたのかな。あと、イー・フー・トゥアンが「田園へのあこがれみてえなのは、古代に都市らしきものが出来たときから同時に生まれたくらい古いもんだぜ」みたいなこと言ってた気がする。
まあともかく、当時の腰越は東京生まれ東京育ち教養ありそうなやつはだいたい友だちの著者からすると、自然の中の暮らし、シンプル・ライフ最高! みたいな具合なのだ。それで、ちょっと電車に乗ったりして横浜の都会に出るのがいいんだ、みたいなことを言ってる。やはり恵まれた階級で、自家用車など乗り回している記述も多い。
私は、たまに江の島電車で藤澤へ出るが、大概は龍口寺からバス専用道で大船へ出る。片瀬と津村境の峯を開いて左手には鵠沼の濱から丹澤、大山、富士、箱根の連山を眺め、右手には鎌倉山の峯々谷々の間から七里ケ濱の白浪がちよいと見える。道の両側には自然と野生の山櫻、山つゝじなどが春色を彩り、秋は山楓、櫨の紅葉、荻、すゝき、女郎花などの秋草が文字通り花道のように自動車道を飾つてゐる。私は、こんな美しく整つた自動車道を外に知らない。
「往路帰路」
さて、昭和九年に書かれた風景である。出てくる地名はすべてわかる。が、それを思いうかべることはむつかしい。「龍口寺からのバス専用道」といえば、俺が子供のころには目白山下から江ノ電に突き当たるまでの部分が有料で、黒いカバンを首からかけたおっさんが一人、50円の料金を回収しようとしていたものだった。もっとも、そんなに厳密なものでもなく、土地の者はいざしらず、どこかから遊びに来た人があれを有料道路とは思うまい。あれが普通の道になったのはいつのことだったかしらん。

まあともかく、バス専用道とは、あの道のことを言うのだろう。今で言えば、湘南モノレールの下を走るあの道である。「片瀬と津村境」といえば、俺の住んでいた津西、片瀬山付近の高台あたりのことだろうか。それとも、もっと先だろうか。左手に富士山というのはわかる。「峯々谷々の間から七里ケ濱の白浪がちよいと見える」というのは、今もモノレールにでも乗れば見られる光景、俺が実家から見ていた光景にほかならない。ただ、「鎌倉山の」と言われるとよくわからん。ここは固有地名の「鎌倉山」ではない、と解釈すべきか。だいたい、俺の頭の中の大船への道は、鎌倉山を登っていくのだし。いや、それとももっと見通しがよかったのかもわからん。よくわからない。花道のように、というのはどのあたりのことか。鎌倉山の桜はソメイヨシノのはずで、そろそろ寿命を気にするころではないかしらん。
さらにこのあたりのこと。
江の島縁起によると、大昔津村の奥の深澤といふところに五頭の悪龍が住んでゐて、頗るに里人の子を食ひ、里人をして悲嘆の涙にくれさせたのを、江の島辨財天女が美しい身をもつて之を教化調伏して山と化した。今の龍口寺のところが即ち、その龍の口なのである。この神話は、恐らく往昔深澤あたりに大蛇が跳梁して人びとを苦しめた印象から生まれたように解釋されてゐるが、私はむしろあの深澤鎌倉山から江の島へかけて走つている丘陵の容が、いかにも龍に似てゐるところから来たもので、この山容を説明する為に生まれた神話ではなからうかと思ふ。
「蛇」
「深澤鎌倉山から江の島へかけて走つている丘陵の容」、なるほどと思える反面、完全に切り崩されて、住宅地になってます、という感じもする。ただ、西鎌倉のメーンストリートやあのあたりの坂道を思えば、なるほど龍のように丘が伸びていたというふうにも思えてくる。しかし、この神話を「海水浴シーズンの催し物」として「ページェント劇」にでもしたらいいんじゃないかと言ってておもしろい。というか、実際に企画してなんかやったらしいし、腰越状の萬福寺でのイベント演目などにも関わっていて、当地の文化人の面目躍如といったところが伺える。
土地の話に戻る。
青海に冷き秋の水おとす
川二つある腰越のさと(晶子)
腰越のような海水浴場の秋は、ことさらに淋しい。夏の盛りを思ふさまを讃えた宴の跡のように人波がさつと引いてしまふと、濱邊には都人の海水用具の残骸が、むざんに白浪にもてあそばれてゐる。海の色はいよいよ青く冷く透きとほつて、そこに注ぐ二つの川の水脈が今さらに、きびきびと動いてゐるのが感ぜられるのである。
「津村の秋」

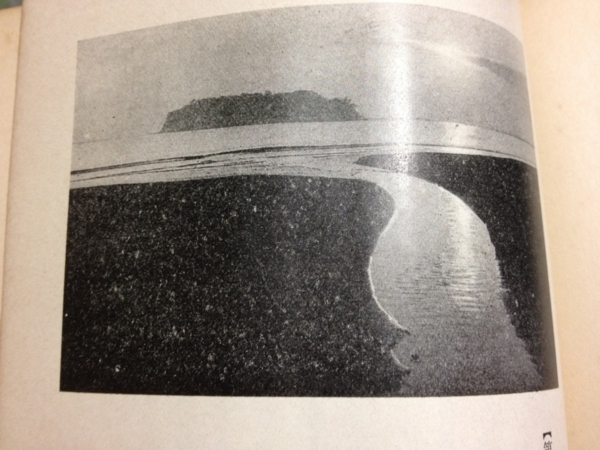
で、この第三句は「川二つあり」と素人ならやりたいが、実感を偽るという。なぜならば、田邊の八戸から流れ出て七里ケ浜に注ぐ行合川と、津村の奥から流れる神戸川はまったくべつの流れだからだ、という。俺の知っているのは著者曰く「いつしか、どす黒い水の流れるどぶ川となりはてた」神戸川(ごうどがわ)の方であって、七里の方はよく知らん。写真は最近の神戸川と、この本に載ってたもの。
秋風が吹きそめると、私はもう汐の香が鼻について、海には背を向けて、津村の山ぞひに自ら足が向くのである。津村は南面に海がひらけてゐるだけで、三方山にかこまれ、恰も鎌倉を小さくしたような地形である。
と、ここがすばらしい。鎌倉の端にあってほとんど藤沢のようなものだが、俺は海のほうを見下ろしては、天然の要衝たる地形に思いをめぐらしたものである。ちなみに、ある時この津村の山のなかに新築の家が建って、著者はどんな人がこんな不便なところに住むのか不思議に思ったという。結果として、大船行きのバスが通り、津村の停留所ができたので、浜側の人より地の利をえたわけだが。後の後にまた、モノレールなどできて万々歳だろう。まあ、大船に出る場合のことだが。
龍口寺から大船へとバスの専用道路が通じない前は藤澤がこの地の門戸になつてゐた。はじめ驛附近の新開地だけしか知らぬうちは、淋しい宿場町だと思つてゐたが、やがて遊行寺の先の本町を通つて見ると、実に堂々だる老舗問屋が軒をつらねて、なるほど昔はさこそと思はせる町の品格を見せてゐるのである。さすがに時宗の総本山遊行寺の所在地である。
「藤澤」
私は鎌倉といふ近代都市よりも、むしろ藤澤といふ東海道の宿驛の方に興味がひかれる。
「藤澤」
さて、一方藤沢の話である。俺などからすると、藤沢駅付近といえばあのあたりで一等栄えた土地であって、淋しさなど感じさせないわけだが、このころは鎌倉が近代都市というのだからまるで話が違う。まあ、鎌倉駅周辺は、この当時の「近代都市」の感じが微妙に残っていていいとも言えるか。さて藤沢は遊行寺の方。なるほど、つい数年前にも行ってみたが、あのあたりというのは何かいい雰囲気がある。遊行通り、聖智文庫、白旗、藤沢橋。義経の首洗を称する地なども、道路から一本奥に入ったところに、妙にぽつねんとあったりしていい。遊行寺があるかぎり、いくらか門前町の雰囲気は残り続けるのかどうか。

この「藤澤」、後半には町長が出てきて、こんな会話をしている。
―この高座郡は日本でも有数の豚の名産地です。それを紹介する意味からも、田中博士式の豚料理を開業したらよいと思ひますが、驛のどこか近所で。併し何といつても藤澤では尻込みしますね、鎌倉ならとにかく。
―豚は結構ですね。あの近頃流行のトンカツなどは世界的な美味だそうですね。
高座豚といえば、なんとなく近頃耳にするようになった地域ブランドと思っていたが、昭和十二年にはそうであったのだった。と、思いきやwikipedia:高座豚によると、はじまりは明治の頃で「横浜港開港に伴う外国人居留地の豚肉需要に応えるため」だったが、一度途絶え、復活したのが1985年というのだから、俺の感覚は間違っていなかったかもしれない。
……とまあ、あとはわりと蓼科とかに登山に行ったりとか、坪内逍遥先生の思い出とかそんなんだが、俺にとっては十二分に元をとれたといっていい。あと、こんな言葉の話がかいま見られるのもおもしろかった。
お前といふ言葉は、東京では目下に対するもので、決して敬称にはならない。ところが、この地方では、お前といふのは多少改まつた敬称なので、例へば子が親に向かつていふ対称なのである。東京でお前に相當する言葉はわれである。だからお前さん、お前様などとは大敬称なのである。宅へ出入りの職人の妻女を、おかみさんと呼ぶといかにも恐縮してゐる様子で、どうか勿体ないから、おかみさんは止めてくれといふ。若ければねえさん、年増ならばおばさんとでも呼ぶのが相当なので、おかみさんは大店の主婦の敬称なのである。これは東京でも最近までそうであつたが、いつかしら、長屋のおかみさんといふ風になつてしまつたのである。
敬称の移り変わりとか、なかなかおもしろげじゃないですか、と。それでさらに、最近は「御」の字を濫用する風潮があるといって、こんなことを言う。
それで思い出すのは、例の長唄の勧進帳に有名な「判官おん手を取り給ひ」といふ文句である。これは判官が家来の辨慶の手を取る處だから「おん手」は、をかしい、何とか訂正の必要ありといはれてゐる。
勿論、厳格にいへば敬語法の間違ひであるが、私は、昔の作者が、思はず「おん手」と書いた気持、又、今日でも「おん手」と唄つても少しも不自然に聞えないその気持を汲んでやらなければならぬと思ふ。「いづれ後ほど、御電話で申し上げます。」「失禮ながら御手紙を差し上げます。」といつても、別に笑はれもしないが、この電話なり手紙なりは、自分のものであるから「御」をつけるのは問題である。然し、つまりは先方に触れるものだから、そこに敬称をおのづから用ひたくなるといふ気持である。
敬称は所詮、気持の問題である。私は判官の「おん手」を是認したいと思ふ。
とか、こんなんいいね。勧進帳しらねえけど、俺だって日常で「それじゃあまた、お電話差し上げます」とか言っちゃったとき、「あ?」みたいに思うんだけれども、所詮は気持ち、それでいいじゃねえか。しかしまあ、腰越と言葉というと、のちにここが言葉狩り運動の発祥地になったりするんだけれど、それはまた別の話、ということころで。
おしまい。

関連書?
[rakuten:takahara:10061991:detail]

- 作者: イーフートゥアン,小野有五,阿部一
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2008/04/09
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 31回
- この商品を含むブログ (23件) を見る